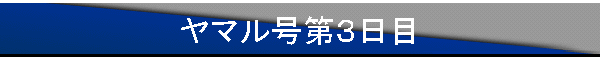8月23日(金)
北緯83度
起床し窓の外を見ると、曇り空で少しばかりみぞれが舞い寒そうである。外の気温をスタッフに尋ねると0度、寒そうなわけである。操舵室に上ってディスプレイを覗くと、現在地は北緯83.28度・東経43.08。緯度上ではムルマンスクから極点までのおよそ半分の地点まで来たことになる。
洋上を毎時20マイルで走っていたヤマル号も、流氷地帯に入った昨日の午後からは、15ノット(27キロ)にスピードダウン。ほぼ全面流氷のこのエリアでは更に遅くなり、10~12ノット(18~20キロ)。
北極点、北緯90度まではあと7度、距離数で390マイル(750キロ)ほどである。このスピードでいくと、あと40時間ほどということになるが、極点に近づくにつれて氷の厚さが増すことを考えると、極点到着は明後日の昼頃になりそうだ。
途中、高さが20メートルを超す氷山に遭遇する。こんもりとした丘のように氷原の上に顔を出した氷山は、北極海では珍しいほどの大きさである。流氷同士がぶつかり合って出来た小山が、氷に閉じこめられて出来たものらしい。
百メートルを超す厚さの棚氷が崩れてできる南極海の氷山の中では、この程度のものは小さい部類に入るが、北極海ではこれほどの規模の氷山は少ないようだ。
北極点踏破
午前中、今回のツアーのプロジューサーであるポセイドン社のエクスペディションリーダー、ビクトル・ボヤンスキー氏の「犬ぞりによる北極点踏破」の話を聞く。
彼は現在サンクトペテルブルグにある北極・南極研究所の館長であるが、39歳で南極横断の偉業を達成している大変なアドベンチャーでもある。北極点に立つのはなんと今回で25回目だというが、その内の一回が、今日の話の犬ぞりによる到達である。
スライドを交えての極点到達までの苦労話しを聞くと、流氷の氷原を踏破することがいかに大変であるかが実感される。北極海が全面氷結した冬は氷点下60度を超す寒さが待ち受け、氷点下30度位まで温度の上がった春先からは、たくさんのクレパスが待ちかまえているのだという。
安全で快適な船とヘリを利用し、艦内ではTシャツ一枚で過ごせる我々の旅は、歴代の探検者たちの目から見たら、幼稚園児の遠足のようなものだろう。
毎日の食事は地下デッキ1階のダイニングルームでとるが、今日の昼あたりから食事中に受ける砕氷の騒音と衝撃波が次第に大きくなってきた。ガリガリという氷を破壊する音と、ズドーンという下から突き上げる衝撃はまるで巨大な直下型地震に遭ったようだ。中でもその度合いが強烈なときは、恐らく2メートル近い厚さを砕氷しているのだろう。
南極大陸横断
午後、氷原を進むヤマル号の姿を眺めようと、ヘリコプターに乗って上空を飛ぶことになった。高見から眺める小さなヤマル号は、まるで氷原に取り残された深紅の箱船のようだ。しかし、高度を下げるにつれ、砕氷する力強いヤマル号の勇姿が見えてくる。
帰艦後、ミーティングルームでポセイドン社のスタッフの一人として参加している船津圭三氏の「南極大陸横断220日の挑戦」の講演が行われた。
1989年12月から1990年3月にかけて行われた6ヶ国、6人の隊員と犬36頭による、世界初の南極大陸横断6000キロの体験談である。この探検には、舟津氏と一緒にビクトル氏も参加している。
「International Trans-Antarctica Expedition」遠征隊の構成メンバーは、フランスのジャンルイ・エチエンヌ、アメリカのウィル・スティーガー、ソ連のビクトル・ボヤルスキー、中国のチン・ダホ、イギリスのジェフ・サマーズ、それに日本人の舟津圭三氏であった。
我が国では大々的にマスコミで取り上げられなかったため、あまり知る人が少ないようだが、彼らが横断を達成しロシアのミルヌイ基地に到着したとき、6ヶ国の大統領や首相から自国への招待状を兼ねた祝電が届けられたというから、世界中から注目された大変な挑戦だったことがわかる。
その後、彼らは実際に各国に招かれ、大統領や首相の歓迎レセプションに参加している。アメリカはブッシュ、ソ連はゴルバチョフ、日本は海部総理の時代であった。
船津氏は8年ほど前にアラスカに移住し、現在フェアバンクスに居を構えて犬ぞりレーサーとして活躍している、1962年生まれの快男児である。
ネプチューン祭
夜に入り、小雪の舞い散る白夜の甲板で、「ネプチューン祭り」が行われた。ギリシャ神話に登場するポセイドンと同じ海の神様、ネプチューンに航海の無事を祈る祭りだ。
祭りには乗客の外に艦長以下の乗組員、ポセイドンのスタッフ一同が参加。ハイテンポのロシア音楽に乗って踊る輪の中に、ホットウイスキーならぬホットワインで和やいだ乗客も加わり、いやが上にも盛り上がる。
まるで月遅れの盆踊り大会が行われているようだ。楽しいひとときを過ごすことができた乗客の顔に笑みがこぼれる。流氷に囲まれたヤマル号甲板で過ごした、思い出に残る一夜であった。