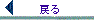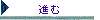先ずは、中国のンガバ県のバルマという村に潜入取材したロイターの記者が発信した、チベット人女性の焼身自殺のニュースをご覧頂
きたい。
[バルマ(中国) 6日 ロイター]
-
今年3月、チベット人女性のカルキさん(30)は、中国四川省のチベット族自治州バルマの僧院に頻繁に訪れるようになった。細身で頬が赤らんだカルキさんは、4児の母親で敬けんなチベット仏教徒だ。
肌寒い3月24日の午後、カルキさんは200~300人の参拝者とともに僧院の門の外に立っていた。その後、自らの体にガソリンを浴びせ、マッチで火を付けた。炎は瞬く間に全身を覆い、カルキさんは帰らぬ人となった。
その時、カルキさんは言葉を叫んだが、誰も聞き取ることはできなかった。目撃者の話では、カルキさんが死亡するまで15分もかからなかったという。
カルキさんは、この1年間で焼身自殺を図った9人目のチベット人の母親となった。2009年以来、少なくともチベット人117人が、中国政府のチベット政策に抗議して焼身自殺を図り、収束する兆候は見られていない。
焼身自殺を図ったうちの90人以上が死に至っており、最近では5月29日に青海省で死者が出た。カルキさんは、バルマのあるンガバ県では39人目の焼身自殺者となった。チベット人が多数を占める同県は、2012年から劇的に増加した焼身自殺の中心地だ。
1950年代の初めから60年にかけて、中国政府は人民解放軍を使ってチベットを侵略、占領。その結果、100万人を上回るチベット人が殺され、仏教寺院や伝統ある建造物、長い歴史を伝える書籍や芸術品などそのほとんどが破壊され、文化の継承を止められてしまった。その詳細を知りたい方は『
中国はいかにチベットを侵略したか 』(講談社インターナショナル刊)の一読をお勧めする。
毛沢東主席率いる中国共産党のこの残虐非道な行為は、20世紀最大の悲劇の一つとして語り伝えられているが、世界大戦終了後のどさくさに紛れて行われた
ものであるため、見過ごされて来た面も多分に残っている。中でも目を覆いたくなるのは、たくさんのチベット人僧侶を逮捕し巨大な穴に投げ込んだ後、糞尿をかけてなぶり殺すという、人間としての誇りをも踏みにじる極悪非道の行為である。
宗教心を持たぬ国民とはいえ、人間として許されること、許されないことの分別ぐらいはわきまえているはずである。単に人を殺傷する行為を通り越したケダモノ以下の行為である。いやケダモノとてそのような行為はしない。それにしても、なんとも空恐ろしいのは
、そうした行為をなんとも思わない中国共産党が今もなお政権の座についたままであり、その先兵を務める100万の人民解放軍
が戦力を日に日に充実していることである。
前主席の胡錦涛氏が国家のトップに立てたのは、チベット自治区の責任者であった時、権力を駆使してチベット人民を共産党の政策に従わせた功績によるものであることは、知る人ぞ知るところで
あり、胡錦涛氏の隠されたおぞましい経歴の一部でもある。
つい先日まで、そんな人物が国家を率いていたことを考えれば、共産党政権の恐ろしさが今も何一つ変わっていないことが分かるはずだ。体裁を取り繕い、情報封鎖によってその恐ろしい実体を隠して来ているだけである。
それ故に、チベット自治区では焼身自殺という痛ましい行為が今もなお途切れることなく続いているのだ。こうした行為が頻発してチベット人の対中国感をさらに悪化させることは、チベット自治区を統括している共産党役人にとっては致命傷となる。
それ故、先日、焼身自殺を遂げた夫婦に対して、チベット自治区を統治する共産党のトップは、「これは夫婦げんかを焼身自殺に見せかけたもので、人民を惑わす馬鹿げた行為である」という、
信じ難いコメントを発表し、矛先をチベット人に向けている。
焼身自殺、それは決して夫婦喧嘩の後始末に使うほど単純な行為ではない。おのれの体に油を注ぎ、火をつけて我が身を焼くという、苦しみの極みを通して民族の苦境を相手に伝えようとする行為である。そうした必死の思いが、おのれの立場を守るために夫婦喧嘩で片付けられたのでは、死んでも死にきれない。強い
怨霊となって中国という国家を呪い続けることになることは間違いない。
同じことが117人の焼身自殺者全ての行為に当てはまるはずだ。彼らの多くが僧侶であったことを考えると、憎しみや恨みの心がいかに強大なエネルギーとして、中国全土に蓄積されて来ているか、想像に難くない。そうした怨念は国家のカルマとなり、また中国人一人一人
のカルマとなって火を噴くのを待っているのだ。
その時期は刻一刻と近づいているものと思われるが、負のエネルギーが巨大である分、それは他に類を見ないほどおぞましいものとなるに違いない。自国民同士が奪い合い、撃ち合い、殺し合うその情景は想像しただけで鳥肌が立ってくる。
実は中国が背負ったカルマには、もう一つ他国にはない、とてつもないカルマがあるのだ。それについては回を改めて記すことにする。