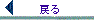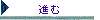前回、「チベット・母親の焼身自殺」で中国という国家が抱えたカルマについて記した。カルマには個人のカルマだけでなく、団体のカルマも民族のカルマも国家のカルマもある。間違った教えを説き続けている宗教団体の持つカルマも
実は恐ろしいカルマの一つなのだ。
個人が多かれ少なかれカルマを抱えているように、全ての民族や国家もそれぞれがその歴史の中で為してきた行為によって発生した、様々なカルマを持っているのである。日本には日本国家としのカルマ、米国には米国
国家としての建国以来のカルマがあるのだ。
我が国や米国のカルマについてはすでに講演会で話した通りである。今回は、前回に続いて中国が抱えたカルマについて記すことにする。
共産党政権国家として世界に君臨している中国のカルマの一つが、「チベット・母親の焼身自殺」で記したように、大義名分のないチベットへの侵略行為と占領の際に行った非人道的行為、さらには多くの僧侶
たちの焼身自殺につながるカルマである。
中国が抱えたもう一つのカルマとは何か? それは、中国共産党政権が「一人っ子政策」という名の下に行ってきた人減らし政策によって産まれたカルマである。つまり、1971年から人口抑制に取り組み、1979年から一人っ子政策を開始した結果、毎年約1000万人の妊婦が中絶することによって生じた嬰児殺害のカルマなのである。
「子供の人工中絶がそれほどのカルマを生じるのだろうか?」と、疑問に思われる読者も多いかもしれないが、この世での生活を夢見て生まれて来る魂にとっては、中絶はその願いが絶たれる許しがたい行為であるのだ。その結果、彼らは強い憎しみや恨みをこの世に残すことになり、その多くが不
成仏霊としてこの世をさまようことになるのである。
人道的見地から許される中絶も無いわけではないが、その多くが出産する側の身勝手な都合によるものだけに、誕生を拒絶された子供の魂は納得できないケースが多いのだ。中国ではその多くが親が産みたいと思っているのに、国が政策としてそれをストップさせているのだから、当然そのカルマは国家に帰することとなる。
これが中国国家が持つもう一つのカルマとなっているのだ。
しかし、同じカルマを個人が背負うことになるケースもある。施策施行後に一人しか出産できないことを承知の上で、しっかりした避妊対策を取らない夫婦には
、それなりのカルマが生じることにもなるからだ。また、家系の行く先を考えるために、生まれた子供が女児だった場合には、死産として処置してしまうケースも多いようである。その場合には当然ながら自己本位の殺人行為として
、両親やその家系にカルマが生じることになる。
中国政府の要人は一人っ子政策の実施で「4億人の人口増加を回避できた」(フランスRFIラジオ)と得意げに語っている。つまり40年間で4億体の嬰児が中絶されたというわけである。なんとその数は先の世界大戦で亡くなった戦死者の数百倍に達している
。これだけでも恐ろしいことだが、私は、一人の母親が数回の中絶行為を行っている可能性が大であることを考えると、その数は十数億に達しているのではないかと思っている。
政府の行ってきたこうした強制的な人工中絶に反対してきたのが盲目の人権活動家・陳光誠(ちんこうせい)氏である。中国政府は彼を長い間自宅軟禁の状態にして活動を抑えて来た。彼がさらなる弾圧を予期して米国大使館に駆け込んだのは、2012年4月。その後、幸いにも5月に渡米してニューヨーク大学の客員研究員となることが出来たが、先日来のニュースでは、中国政府からの圧力で大学を追われることになろうとしている
ようだ。また中国は新たなカルマを背負うことになりそうだ。
今やこうした堕胎によって、この世への誕生を拒絶された膨大な数の魂の恨みや憎しみのエネルギーが、幾重にも、幾重にも重なって中国全土を覆い尽くしているのだ。
4次元的な負のエネルギーを感じる事の出来る人には、なんとも空恐ろしい情景が目に映っていることだろう。そうした空の下で暮らしている14億人の民は遠からずしてその負のエネルギー、カルマを刈り取ることになるのだ。
一方、様々な理由で子どもができず、さらに男の子を望む家庭が多いために、闇業者がはびこり誘拐した子供を人身売買するケースも多発しており、その数は年間20万人を超している。わが子を誘拐された親は全財産を投げ打ち、藁(わら)にもすがる思いで
、わずかな手がかりをたよりに全国各地に足を運んでいる。
これは、命を絶たれた子供達の恨みのエネルギーがそうさせているものであるが、まだそれは本格的なカルマの刈り取りのほんの序章に過ぎないのだ。これから先に待
ち構えているのは、血が血を呼ぶ国民同士の血みどろの争いである。
カルマの解消には、そのカルマを刈り取るのに最適な手段が用いられる。共産党政権を崩壊させ党の幹部を地獄へと導くカルマの解消には、それが最も適した刈り取りの手段なのだ。
隣国に位置する我々がその恐ろしい情景を目にするのは、決して遠い先のことではなさそうである。